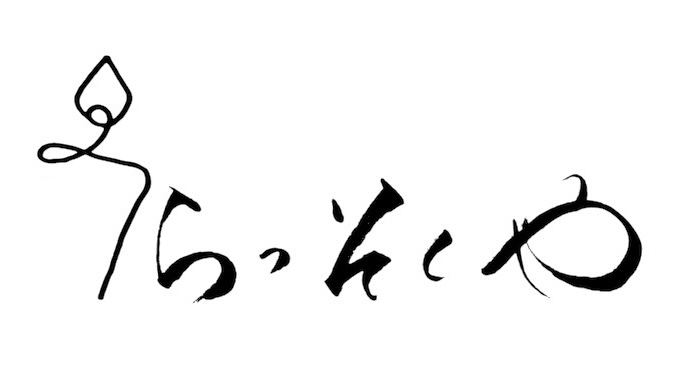和ろうそくとキャンドルって違うもの?⑴
和ろうそくとキャンドルって違うもの?
こんにちは!らっそくやのicoです。
初めてのブログ投稿です。
よく和ろうそくとキャンドルの違いは?と聞かるので、先ずはそのことについてお話しいていこうと思います。
和ろうそくとキャンドルは基本的には同じものです。
よく、時々全く別物と表現されるのを見聞きすると思いますが、どちらも「火を灯すもの」です。
しかしそれぞれにいくつか特徴があります。
●材料の違い
キャンドルは、石油が原料のパラフィンを使用します。

形成がしやすく、様々な形や色に簡単に加工できます。
物によりますが、煙も少なく使いやすいです。形が変えやすいため、可愛いものやカラフルなものが多くあります。
和ろうそくは、櫨の実(はぜのみ)を使用します。

櫨の実というと、聞きなれない方もいらっしゃると思いますが、小さい頃、田舎に行ったり山登りをするとき、「赤い葉っぱは触ったらダメ‼︎」と言われた記憶はないでしょうか?
紅葉の綺麗な秋の山中でも、ひときわ美しい赤い葉っぱで、手に触れるとかぶれてしまう…あの葉っぱです。

少し敬遠されがちな櫨ですが、この木になる実は、和ろうそくの材料になります。
今では、その性質のせいもあって伐採されることが増え、昔はよく見ていた櫨の木もあまり身近で見ることはなくなりました。
私の出身は鹿児島ですが、江戸初期にその技法が伝えられた薩摩藩は櫨の栽培を盛んに行い、1867年(慶応3年)パリ万博博覧会にて櫨の実から採取した木蝋(もくろう)を薩摩の産物として出品したと言われています。
学生の頃、和ろうそくの研究をしていた私は、薩摩藩の木蝋(もくろう)の歴史にとても縁を感じたものでした。
ただ、実際は薩摩藩の木蝋づくりは藩が潤うため、農民に厳しい統制の上で栽培と製蝋(せいろう)を課したものでした。
そういう事情もあり、明治維新後は鹿児島の櫨の木が多く伐採されることになったのです。
薩摩藩の政策に、たいへん苦しめられた農民にとって櫨は忌み嫌う存在であり、この歴史はあまり鹿児島の人も語らないようです…。
とても残念です。
他に違いは?
●芯の違い
よくみなさんが使われているキャンドルは、細い凧糸のような芯を使用します。
※漂白した木綿を編み込んでロウを染み込ませたもの
和ろうそくの芯は、灯芯(とうしん)と言って、和紙に藺草(いぐさ)のズイを巻きその上を真綿で巻いて止めているものを使用します。
キャンドルの芯と比べて、和ろうそくの灯芯はかなり太いものになりますが、これは木蝋(櫨の実から採取されたロウ)がたいへん粘りが強くこの灯芯でないと吸い上げることが出来ないからです。
キャンドルにも、蜂の巣から精製する蜜蝋(みつろう)や大豆から作るソイワックスなどもありその種類は様々です。
●燃え方の違い
和ろうそくの炎は、キャンドルの炎よりも大きなものになります。
和紙に藺草(いぐさ)のズイ、真綿を巻くことで灯芯(とうしん)も太いものになります。
そしてこの芯作りの工程により、芯自体に空洞ができ空気の通り道ができます。
そのため、和ろうそくのもう一つの特徴である「炎のゆらぎ」が生まれます。
風が吹いていなくても、炎がまるで生きているように縦に伸びたり縮んだりさまざまな表情を見せてくれます。
話は脱線しますが…昔お茶会などの際、和ろうそくの灯りだけでふすま絵を嗜んでいたそうです。
お茶会?夜にお茶会?と謎がたくさんありますが、この「炎のゆらぎ」により表情の変わるふすま絵についてお茶を飲みながら、お話していたかと思うと…とても興味が湧きます。
手始めに、家族を誘ってみたいと思います。
そして和ろうそくの燃え方のもう一つの特徴は、炎が大きいので、ちょっとやそっとの風では消えません!!
…ここまで和ろうそくとキャンドルの違いをお話ししてきましたが、すみません…まだまだ終わりません(^^!)
次回、続けてお話ししていこうと思います!!
良い1日を!
関連情報